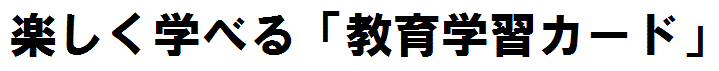「教育学習カード」の効果
記号・文字・植物・絵カードの4枚のカードにより構成
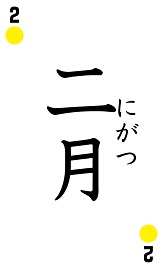 |
 |
 |
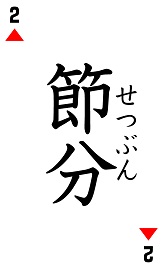 |
| 記号 | 植物 | 絵 | 文字 |
1 楽しく学べる
2 コミュニケーションツールとしての活用(ルールとマナーも学ぶ)
3 言語教育への変換(他教科との連携)
4 「1対1」対応(特別支援が可能)
5 カードの数字・マークをなくしてのステップアップ
6 地域活性化・図書館活動での導入部・家庭学習との連携・海外研修の日本紹介・文化交流の一助・老人ホーム
などでの効果的な活用など
「知識」の定着率だけではない、多くの<効果>が、目に見えることから、目に見えにくいことまで含めて獲得できる。
コミュニケーションツールとしての活用は、仙台市愛子小学校での学年の枠を越えた支援活動として。課外活動での活用。
言語教育での効果は学会での発表によって、多くの人の共感を得た。マークや数字のないカード実践は、「日本大学付属高等学校夏期研修会」で国語の先生方に実感していただいた。「文化交流の一助」については、フィンランドでの実践活動で確認した。
アンケートデータによる検証
 | 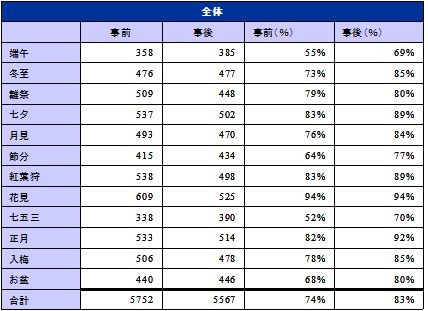 |
| 横浜市の公立小学校(1年生) | 日本大学中学校(1年生) |
1 小・中学生ともに総合的な定着率(正答率)において、9%の伸びがある。もちろん個々の定着率には差があるものの、
年齢などに関係なく教材の効果があることが分かる。(「コミュニケーション指数」なるものを想定できる)
2 地域差や年齢差あるいは言語差などの「差異」をこえるところにこのカードの特徴がうかがわれる。
3 カードの内容(記号としてのもの)を変えることで、何をデータとして求めたいかの選別ができる。またそのデータから環
境・年齢・男女などの位相差を検出した。
4 漢字の読み書きのデータの差異(事前事後の差)は基本的にコミュニケーションの差にあると思われる。
5 どの程度の「興味」「関心」「今後の展開」につてのデータ取得は、裏面の別アンケートで行った。その結果興味関心の
高さはぬきんでていた。
6 上記で言うところのコミュニケーションはゲーム性と集団内での帰属感覚から生じていると思われる。
詳しい研究内容についてはこちら